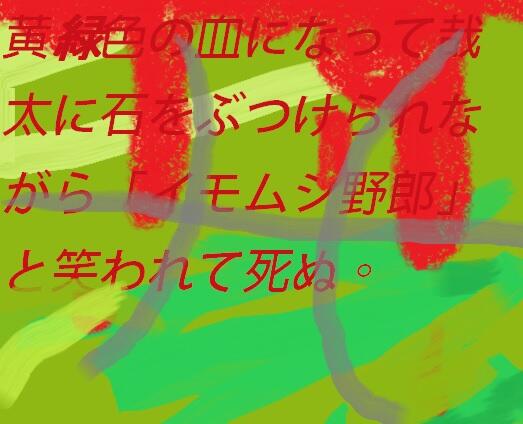Novel
【男主夢】03*男主【星座彼氏が原因で死ぬ】
星座彼氏が原因でアッサリ死にますシリーズ
主人公は哉太のクラスメイト
case2.Pisces
うぅ…どうしよう…目が痛い…。も、もしかして充血してきてる…!?どうしよう、今日はうっかり目薬忘れてきちゃったんだよなぁ…。
「おーい、名無し。」
「うわぁっ!?」
「うおぉ!?」
僕はどういうワケか、生まれつき血が濃い黄緑色をしてる。虫みたいで気持ち悪いんだけど、病院で調べてもらったらどうやら普通は存在する筈のヘモグロビンじゃなくてヘモバナジンっていう物質が代わりにあって、それが酸素を運んでるとか…云々って(ちなみに、そもそも虫は酸素を取り込む構造が他の動物と異なるみたいだから、虫じゃないよ僕は!)。…あっ、そう、だから、僕は誰かの前で怪我をするわけにはいかないんだ!星月先生と担任の陽日先生は勿論知ってるんだけど、他はクラスの誰も知らないわけで…。バレたらきっと嫌われちゃうよ。
肌は"少し黄色いかな"って感じだから、ミカンを食べ過ぎちゃって、って言えば全然問題ないし、それに僕は活発な方じゃないから怪我をする事だってまず無い。でも怪我をしてなくても油断は禁物で…、何が怖いって、目が充血しちゃう時!こればっかりはどうしようもなくて、充血を抑える目薬を差して対処するしかないんだよね…。白目が黄緑色してたら、誤魔化しようがないから。
つまり、目薬を忘れて…おまけに七海君に声を掛けられてる僕は今物凄くピンチ!大ピンチ!あわわわ…っ とにかく、切り抜けるしかないッ!
「ど、どうしたんだよ?んな驚かなくたっていいだろー。」
「ご、ごめん、ボケーッとしてたんだ!」
座って鞄を漁っていた僕は七海君の方を向き、手を顏の前で合わせてギュッと目を閉じて謝る。流石に七海君の方を見ないのは、誤魔化すとか以前に失礼だもの!でも目を閉じたままもおかしい、よね…。薄目だったら大丈夫かな、と思って僕は恐る恐る七海君を見上げた。
「ったく、相変わらず抜けてんなー!
ああ、そうだ。なぁ、昼飯一緒に食わねぇ?」
「…あっ ホントだ、もう昼休み…。」
手元の時計に視線を落とすと、確かにもう昼休みだった。うわーっ 充血が気になって忘れちゃうなんて!僕が思い出したように「お腹空いたぁ〜」とヘナヘナすると、七海君は大笑いしながら僕の頭を叩いた。
「ほら、行こうぜ!」
「うん!」
「あー、いい天気〜!」
中庭の一角に腰を下ろしながら、僕はググッと身体を伸ばす。秋の穏やかな陽気と心地いい風…、今日は所謂"絶好のピクニック日和"だなぁ…。目の痛みも引いていて、こっそり鏡で確認したら充血も治まってたから、もう挙動不審にならなくて大丈夫そう(充血とかの確認用に鏡を持ち歩いてるんだ)。
購買で買ってきたパンを二つ取り出して、どっちから食べようか考える。うーん、どうしようかな…メロンパン…焼きそばパン……、…焼きそばパンにしよう!僕がバリッとパンの袋を開けていると七海君も同じタイミングでパンを開封していた。
「コロッケパンも美味しいよねぇ。」
「あぁ。ボソボソしてないし、かつ!水っぽくなくてたまんねぇよなー!」
食べながら、七海君が「太陽に、午後の授業サボれって言われてるような気がする」なんて目を細めるのがおかしくて、僕はくすくす笑いながら焼きそばパンを頬張った。でも、サボりたくなっちゃう気持ち分かるなぁー…暖かい。
パンを食べ終わって、緑茶で喉を潤した後に僕は七海君の目を盗んでまたこっそり鏡を覗き込んだ。ソッと舌を出して、舌の"染料"がちゃんと残っている事を確認する。血が黄緑色だから当然舌も黄緑色なワケで…。いくらなんでも舌が黄緑色なのは目立つから、特殊な染料で毎朝舌を赤く染めてから登校してる(幸い唇は若干黄色がかってるくらいだから、何もしなくても大丈夫…)。舌を染めてる染料は飲食をする程度じゃ落ちないんだけど、やっぱり不安になるというかなんというか。以前、掛かり付けの医者に舌に赤い入れ墨をしてみるか聞かれたんだけど…そ、それはなんだか怖いから却下した!
「あーあ、眠ぃ。」
「あっ、ちょ、七海君!?そろそろ教室に戻らないと授業始まっちゃうよっ?」
僕が鏡を鞄にしまっているとその横で七海君が芝生にごろんと寝転んでしまったので、慌てて七海君の方を向いた。あと10分程で昼休みが終わってしまうから、此処でゴロゴロしていたら確実に遅刻しちゃうって!僕は七海君の肩を控えめに揺すって戻るよう急かしてみるけど、当の本人は呑気なもので、欠伸なんかしてる。困ったなぁ…。すると七海君は、肩を揺すっている僕の手をガシッと掴むと、強い力で引っ張った。
「いいから、お前もサボろうぜ。…よ、っと!」
「うわぁっ!?」
不意討ちに驚いてしまい、僕の身体は簡単にバランスを崩す。視界がぐるりと傾いたかと思うと、七海君に引かれるまま彼の身体の上に倒れ…、って、危ない!
「くっ…!」
僕は体重が重い方ではないけど、それでも七海君の細い身体に思い切り倒れ混むのは憚られた。だから、咄嗟に地面に手を突いたんだけど…、ま、まずい…っ 地面に石が転がっていたらしくて、右の手の平を怪我したみたいだ…!
「悪い!大丈夫か!?
ったく、変な気なんか遣いやがって…!」
僕が息を詰めた事で、七海君は僕が怪我したと勘付いたようだ。心配そうな顔で僕を見上げてくる。
「だ、大丈夫!ちょっと石か何かにぶつけただけだし、大したことない、から…!」
ど、どうしようどうしよう…!いつも気を付けていたのに、なのに…よりによって友達の目の前で怪我をしてしまうなんて…!どうやって見付からないように保健室に行こう…ッ?大したことない、と言ったけど、強めの痛みから察するに血が滲んでる事は確実だ!嫌だ…嫌だ…血が黄緑色をしてるなんて事、七海君に知られたくない!
僕が混乱していると、その表情から七海君は僕がかなり痛がっていると勘違いをしてしまったらしい。身体を起こし、「見せろ」と言って僕の手首を掴んで…そして…僕が手を引く間も無く…手の平を、返してしまった。
「……ッ!?」
「あ…っ!」
薄く破れた皮から黄緑色の血がじわりと滲んでいて、それを見た七海君の身体があからさまに強張る。見られた…、そんな…っ
「っ……」
「………」
沈黙が痛い。さっきまで穏やかに暖かかった身体が、急激に冷えていく音が聞こえるようだった。心臓の音は沈黙を破ってはくれないのに、どんどん大きく、速くなり始める。
「名無し…」
「……ッ………」
やめて…、なにも言わないで…!!七海君は優しいから気休めの言葉でも掛けてくれるだろう…けど、本心から"気持ち悪くない"と"思うわけがない"!普通から逸脱しているものから、大抵の人は無意識にでも壁を作る。思想とかなら、関わらないようにするっていう対処行動が取れる。けど僕の場合は"身体的"な、しかも、血液という人間の基盤の逸脱なんだ。思想と違って、相手が"仕方のない事"と表面上だけでも無理に共感しようとして"くれる"。視覚による影響は大きい…。今まで"普通の友達"だと思っていたのに…実はこんな色の血が流れていた、なんて…絶対に気持ち悪いと思うに決まってる…。
「……いい色だな。」
「え…っ?」
ところが、ぐるぐると思考の渦に飲み込まれていた僕の耳に入ってきた言葉は、僕が全く予想していなかったものだった。
「珍しいなー、黄緑色の血なんてさ!」
気持ち悪い、という感情を押し殺した『ごめん』『気の毒に』『誰にも言わないから』。昔、病院で腫れ物に触るような態度でしか接してもらえなかったから、てっきりそれらの言葉が、なるべく僕を傷付けまいとする声色で言われると思った。対等に関わり合える心地好い関係が、一瞬で終わると思った。
そうとばかり思った。
そしたら、何だって…?いい色?そりゃあ珍しいけど…、七海君の目は純粋に、本当に興味津々という感じで…。僕は度肝を抜かれてしまい、ポカーンと七海君を見つめていた。そういえば七海君は身体が弱いって話を聞いたことがある。もしかして、それで共感してくれたり…?
「七海く」
「なあ、もっとよく見せろよ。」
理由はどうあれ少なくとも嫌われてはいないのかもしれない、という希望に僕が表情を明るくさせるのと、七海君が僕の声を遮るのはほぼ同時だった。
「え…っ?」
「いや、珍しいだろ?黄緑色の血とか。…だから、……ちょっと痛いかも知れねーけど…我慢な?」
「う、嘘…っ、何…七海君…!やめ、ッ、うあ゙!?」
ガリッ、
ひんやりとした指先の感触を手の平に感じた次の瞬間には、突き立てられた七海君の爪が僕の傷口を思い切り引っ掻いていった。石で怪我をした所は、浅かったとはいえ歴とした"傷口"だ。そんな所を迷い無く、力一杯に引っ掻かれるのはまるで抉られる様に痛くて、僕は思わずビクッと身体を跳ねさせた。
「お、出てきた。…けど、なんか足りねーなぁ。」
「い、嫌だ…!七海君、おかしいよ!離してくれっ!!」
じわじわと新たに血が滲み出てきて、黄緑色が傷口を覆う。けど血が流れたりするような量ではなくて、七海君は不満気に唇を尖らせた。七海君が唇を尖らせる仕草は、なんだか子供みたいで普段から可愛いとは思っていたけど、"普段と変わらない仕草"が今は僕をただゾッとさせる。七海君が楽しんで人を傷付ける人じゃないのは誰だって知ってる。だから目の前にいる七海君が、まるで違う人に見えるし…そう思いたいのに…っ!その何気ない普段の仕草が、彼が七海君である事を如実に物語っていた。
あまりに突然の出来事に僕は混乱したけれど、逃げないとまずい!と、それだけは分かった。でも、逃げようと右腕を引いても七海君の力はとても強くて、僕の力では手を振り払う事は出来なかった。
「七海君…っ!」
「お前って黄色いなーとは思ってたけど、血が黄緑色だったからなんだな。」
グッ、とまた強く腕を引かれて、恐怖心で身体に上手く力の入らない僕は今度こそ七海君と密着してしまう。七海君は、唇が戦慄き顔が青ざめていく僕を見て小さく笑うと、まるであやすように優しく僕の頭を撫でた。でも僕の右手首を掴む左手にはまだ強く力が込められていて、頭と手首にそれぞれ感じる感覚の違いに神経が戸惑っているのが伝わってくるようだった。
「そんなに怖がるなよ、名無し。」
怖がるな、って…、怖い。怖いよ七海君…!抑えようと思っても、唇の震えが止まらない。そんな僕を見て七海君は目を細めると、僕の後頭部をそっと押して顔を近付かせた。
「っ!?」
そんなに力は入っていなかったのに、恐怖心から僕は逆らえず素直に従ってしまう。白くて整った七海君の顔と突然距離が縮まり、僕は思い出したように息を呑んだ。この距離はまるで…キスをされてしまうのではないかと思ってしまうような…。そう意識したら、さっきまで青くなっていた顔が、内側からカッと火が付いたみたいに熱くなるのを感じた。僕は所謂"赤面"は出来ないんだけど、顔が熱くなるから多分同じ事が起きてる。七海君はそれを察したのか、硬直してる僕の頬に手を当て、感嘆の声を上げた。
「へぇー、赤くならなくっても、ちゃんと熱くなるんだな。」
「あ、あの…七海君…っ」
「あっははは!さっきまで青くなってたのに、面白ぇなー。」
冷たくて気持ちいい手に気が緩みそうになる。だっ、駄目だ!逃げなくちゃいけない!ところがその感触は、僕が再び逃亡を図ろうとするよりも早く…それでもゆっくりとした動作で…僕の唇に当たる。
「んんっ!!?」
(う、うわあ、キス、されてる。)
状況を理解した僕が思ったのは、馬鹿みたいにそのまんまの事だった。頬に添えられていた手がもう一度後頭部に回って、顔を寄せられて、キスをされて、……って、え、え、えっ!?
「っぁ、な、七海く…ッ!んぅぅっ」
「ん…っ」
目を見開いて固まっていた僕は、思い出したように抗議の声を上げ…ようと思った。けれど七海君はニヤリと笑うと、僕が開いた唇の隙間から、……舌を…っ!熱を持った七海君の舌がやや乱暴に捩じ込まれ、それに驚いて僕はギュッと目を閉じてしまう。なんで、なんでキスなんてするんだよぉ、七海君…っ 怖いし、何よりも男だし、嫌悪感しか湧いて来ないと思ったけれど…不思議と気持ち悪さはなくて(かと言って気持ちがいいわけじゃない)、ああ…いい友達だと思ってたのに…と、頭の片隅で残念がっていた。
…この時、一瞬でも他の事を考えていたのが間違っていたのかもしれない。七海君は僕の意識の逸れた一瞬に、僕の舌を強く吸った。
「ん、ぁ…っ!」
誰かとキスをするなんて初めてだし、他人に舌を吸われるなんて以ての外だっ。
身体の力も吸われるような、ぞくりとした感じが舌先から腰まで走って僕は思わず眉根を寄せて呻いた。
「ふっ、ぅんん…!」
自分でも聞いたことのない、鼻にかかった高い声が出てしまい、舌を吸われたり舐められたりする度に抑えきれずに漏れる。抵抗しようと思っても、身体の力が抜けてしまって自分の身体を支えるだけで精一杯だった。こんな状況だっていうのに、なんだか気持ちよくて…僕は、七海君はこういうこと慣れてるのかな、と、また他の事を考えていた。
…警戒心を緩めちゃいけないって、逃げなくちゃいけない、って…分かりきっていた筈なのに。
「――――ッ!!!?!」
『ガりぃッ!』
音、というか感覚を音で表すならこんな感じかな。いや、『ブチッ』という単純な音もあるかもしれない。
僕は咄嗟に、弾かれたように七海君から顔を離した。口を手の平で覆い、バッと身体を起こして後退る。激痛と恐怖で唇が震えて、手で覆っていないと"血が垂れてしまいそうだ"。でも上手く力も入らなくて…唇と手の平を濡らしながら、…黄緑色の血が顎を伝った。
「……ッ」
"七海君に、舌を噛まれた"。それも、どうやったら他人の舌を、そんなにも遠慮なく、思い切り噛み付けるんだ、って、くらいの力で。うっかり自分で舌を噛んでしまった時ですら思った以上に出血したり、強い痛みに襲われてしまうというのに…っ。噛み千切られてはいないけど、まるで千切られてしまったのではないかと感じる程の衝撃に、僕は酷く後悔した。"一瞬でも他の事を考えていたのが間違っていた"!!キスなんかに気をとられていないで、さっさと顔を背けるなりすればよかった!そういえば僕の手首を掴んでいた手は離されていて、さっきすんなり七海君を振り払えたのは最初から舌を噛むのが目的だったからなんじゃないかと恐ろしくなる…。
僕が芝生に座り込んだ状態で動けなくなっていると、その向かいで身体を起こした七海君が背中に付いた葉っぱを払っていた。今は僕を掴む手は無いし、逃げるならまさに"今"だっ!…なのに、今度は腰が抜けて……。ああもう、なんで立ち上がれないんだ!
「うーん、なんか変な味だな…。」
味っていうのは…僕の血の事なのかな。
口の中に溢れてくる血を飲み込んでしまいたい…。けれど、少し舌が動くのすらも物凄く痛くて、唾液と混ざって少し薄くなった血が半開きの唇からたらたらと流れていった。僕が俯いて痛みに顔を歪めていると、立ち上がった七海君の足がこっちに近付いて(と言っても、数歩分も離れてないんだけれど…)くるのが視界に映った。あ、ああ…もう…駄目だ…っ!よくわからない、よくわからないけど…もう、駄目、かも……。そう思って、芝生の緑に溶け込んでいく血の光景をガタガタと震えながら見ていると、
「…おっ?」
ふと、七海君の注意が僕から逸れたのを感じた。そして芝生を踏む音が少し遠ざかり、そこで止まる。何かを見付けたのか…?わからないけれど、とにかくチャンスだった!七海君が離れていったという事だけで足に力が入るようになって、ゆっくりとだけれど身体を起こす事ができた。血は既にワイシャツの襟に染みてしまっている。…でも、それでも…とにかく人のいる所に逃げないと…!!
「う、く…ッ」
立ち上がる為に膝についた右手の痛みに顔をしかめる。あまりに突然過ぎる出来事に混乱しているけど…右手も、舌も、この鋭い痛みが現実を叩き付けてくる…。やや覚束無いながらも立ち上がり、腰が抜けていない事に安堵する。…よし、動ける!七海君の動きを確認している余裕は無い…ッ!早く逃…
「っと、待てよ、名無し!」
早く逃…げようとした。……しかし僕は、またしても逃げられなかった。
走り出そうとした、まさにその時……今までに味わった事の無い激痛が僕に襲い掛かってきた。重く、尖った物が、空気を割り裂きながら後頭部を強く打ったんだ。ゴンッという衝撃に視界がぶれ、痛みの感覚を一手に引き受けた脳が声にならない悲鳴を上げる。
「ぐ…ぁ…ッ!?」
地面に倒れるまでの時間が、まるでスローモーションのように長い…。衝撃の割に漏れたのは呻き程度で、脳は「もっと叫べ」と言いたげにグワングワンと揺れる。む…無理だ、少しの叫び声を上げる事すらできなかった…。
どさりと地面に臥して、呼吸すら忘れて呆然と虚空を見つめる。七海君が重そうな物をを放った気配から察するに、石のブロックか何かで僕を殴ったらしい。まぁ…凶器を知ったところで、もう、遅いか………。血が次々に身体の中から逃げていく…。意識がプツン、プツンと少しずつ消えていく感覚に、痛みが僕の脳を食べちゃってるんじゃないかという錯覚に陥る。手足も、もう動かない…。
七海、くん……。
七海君が僕の顔の側まで移動し、しゃがむ。僅かに動いた目を、僕の顔を覗き込んでくる彼に向けると、…なんだか"懐かしさ"を覚える表情が見えた。なんだろう…?昔、僕もこんな顔を…。…あぁ、そうだ……そうだ…、まるで、子供の時に友達と一緒に…虫を嬲り殺しにして遊んでいた時のような…そんな表情だ。…今となっては、気持ち悪い虫だろうが子供の玩具になっている虫は可哀想だと思うし、自分が玩具にしてしまった虫には「怒っていただろうなぁ」と申し訳ないと感じる。
でも、絶対的な力の前には、虫達は怒りすら覚えないのかもしれない…。……今の僕のように。
「…くっ」
七海君が小さく笑う。
「なぁ名無し…お前の血……すげー懐かしい色だよな。」
もう目を開けていられる余力も無い…。目を閉じるのに従って、意識もいよいよ消えていく。何かを考える力も残っていなかったけど、それでも七海君が次に言う言葉は、本能的にわかった。
狙った獲物が血を流しながら動けなくなっていくのは、何とも言えず興奮する。
もう聴覚も働かないけど、きっと笑いながらこう言うんだ…。
「イモムシ野郎。」
と。
END
【黄緑色の血になって哉太に石をぶつけられながら「イモムシ野郎」と笑われて死ぬ。】
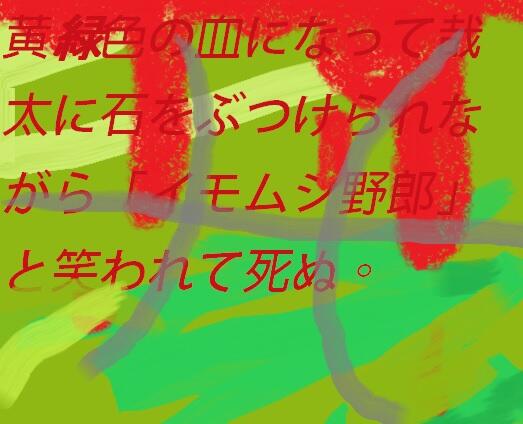
2014.1.17
前へ*次へ#
[戻る]

 携帯モード]
[
携帯モード]
[ URL送信]
URL送信]