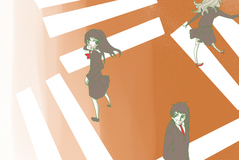素晴らしくない世界
1
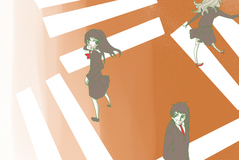
自傷行為、俗に言うリストカットをはじめたのは、「卒業するまで死にません」という本を読んでからだった。学校に友達のいない私は、教室からも浮いていたし、誰もが私の存在を消していた。ここにいるのにここにいない。休み時間はひたすら本を読む。そんな自分が悲しくなって、本に書いてあった、東急ハンズに売っていた使い捨てメスを買うと少しだけ手首を切ってみた。血は出るけど、そんなに深くない。だけど、何か心をスーッと突き抜けていった。
私は常習者となった。
冬は服で隠れるから良いとして、問題は夏だった。少しでも袖が短い服を着ると傷口が見えてしまう。だから夏だというのに私は長袖を着なければいけなかった。これは絶対に人にばれてはいけない。家族であれ、学校のクラスメイトであれ、誰であれ。だけど彼は別だった。認めてくれる。
どうしてだろう、私の生きている意味が見出せなくなっていた。リストカットは毎日のように繰り返し、血を見ては落ち着く。しかしどうしても拭いきれない寂しさというものが、私を包んでいた。心にぽっかりと穴があいている。誰かに、誰かに私の心のうちを開きたい。誰かに救い出して欲しい。だけど私の周りには誰も居ない。
春休みが明け、新学年が始まったある日。私はなんとなく私の住む街の駅ビルの屋上に行ってみた。ステージがあって、そこに向かって結構な数の椅子が置かれていて、サラリーマンや親子連れ、何人かの人が座って話しをしたり、煙草を吸っていたり、いろんな人が居た。
私は椅子に座ると、空を見上げた。今日も私はいなかった。私の存在はなかった。担任は私を呼び出し、「もっとクラスになじめるように努力してみる気はないか」と面倒くさそうに言った。
「佐倉から動いてみなくちゃ何も変わらないよ」とわかっているかのように私を責める。そんなことできたらとっくのとうにやっているよ。
「わかりました」
私はそういうと、もういいですか、と聞き、担任の返事を待たずに職員室を出た。私は聞き逃さなかった。私が担任に背を向けた瞬間ため息をつくのを。
これだから担任というのは面倒だと思った。クラスから浮いている私を世間体から悪いと思い、どうにかしようとする。私は一種の問題児なのだろう。問題児をどうにかするのかが、勉強を教える合間の担任の仕事だ。これで私が教室になじめないでいると、クラスの中心にいるような女子に促したり、学級委員に頼み込んだり、そうしてどうにかしようとする。私はあんたの言うとおりには動かないから。もううんざりだ。こんなことが学校にいる間にあと何回あるんだろうか。勉強はそこそこ出来る。だけどクラスになじめない。遅刻常習者や授業をまともに受けない問題児、私のそれはもっと面倒なことなのだろう。
職員室を出る前、いやもっと前、担任の前に立ってから、リストカットをしたくてしょうがなかった。少しでも何かがあると、切りたくなる。もう中毒だ。ポケットにお守り代わりに持っていた、ピンクのカミソリを握り締め、意味のない担任の話に付き合い、担任のため息に耐え、職員室を飛び出すと、トイレに駆け込む。そしてカミソリを取り出すと腕に刃先をあてがい、一気に横に引く。血が溢れ、その血をトイレットペーパーでふき取ると、かばんの中から絆創膏のようなガーゼを取り出し、それを貼るとトイレに腰掛け、ため息をつく。気分が落ち着かない。これじゃ足りない。でもこれ以上切る気もない。
そうして私は屋上にやってきた。
風が心地良い。憂鬱だった気分も少しだけ晴れたような気がする。空は青々としていて、すっきりとしている。
私は弱虫だ。卒業するまで死にませんという本の著者、南条あやはすごかった。血管まで切ったりして、血が噴出したり、血を溜めてみたり、無駄に献血に足を運び、血を抜いたりしていた。それが本当のことかどうかはわからないけど、すごい人だ。私には到底まねできない。
南条あやを思い、空を見上げていると、悲鳴のような声が響いた。私は思わず声のしたほうを見る。屋上にいた人たちも同様にしていた。
ひとりの女性はしゃがみこみ、立っている女性がその人を見下してた。悲鳴のような声をあげた人はどうやら立っている女性らしい。
「あんたなんか、あんたなんか」
立っている女性は、そう繰り返すと、涙混じりに、「死ねばいいのに」と叫んだ。そのまましゃがみこんだ女性の体を蹴る。蹴られた女性はバランスを崩し倒れる。
「死んでしまえ」
そう言った女性は、きびすを返すと、大股で屋上から姿を消した。
死んでしまえ、という言葉が私を混乱させた。それは言ってよい言葉なのか。それ以前にその死ねばいいのにという言葉は、私が言われているみたいで気分が暗くなった。クラスメイトも両親も、私がいなくなったところで涙ひとつ零さないだろう。私はいてもいなくても同じだ。
叫んでいた女性が屋上から姿を消すと、屋上はさっきのような少し騒がしい場所に戻った。誰も見ないふりだ。見なかったふり。そりゃそうだろう、普通なら関わりたくない光景だ。
だけど私は違った。私が立ち上がると、倒れていた女性もしゃがみんで丸くなった。近くに寄ると、彼女が泣いていることがわかった。そして「死ねって、私、死ねって」と繰り返し呟いていた。
「大丈夫ですか?」
手を差し出すと、女性は私を見上げた。目にはたくさんの涙がたまっていた。女性は私の手をとり立ち上がると、ありがとうございます、と小さな声で言った。
「とりあえず椅子に座りましょう」
彼女を促すと、ふたりで並んで椅子に座る。周りの人が白い目でわたしたちふたりを見ているのがわかった。でも何故か私は彼女を放っておけなかった。
女性はすみませんと、やっぱり小さな声でお礼を言うと、何度もしゃくりをあげて泣き出した。
「私は死んだほうがいい人間なのかな」
そう言って私を見た。状況がわからないから私には何も言いにくい。でも初対面のこの泣きじゃくっている女性に、「そうですね」とは誰も言わないだろう。私が黙っていると、女性はまた泣き出し、もう嫌、もう嫌と呟いていた。ポケットからハンカチを取り出そうとした。彼女に渡そうと思って。そしたら、ハンカチと一緒にカミソリが地面に落ちた。私は動きが止まる。彼女は下を向いていたからそれを見たらしい。女性はカミソリを取り上げると、私に渡す。女性の涙は引っ込んでいた。
「これは?」
と彼女が問う。
「リスカ?」
私が困っていると、「傷見せて」と私を見上げた。
私は言うとおりに袖を捲る。腕は傷だらけだ。ピンク色の一本線がたくさんある。ふさがりかけた傷跡や、さっきしたばかりの絆創膏。それを見た女性はほうと息をついた。
「触ってもいい?」
「え?」
「触らせて」
彼女はそういうと、真っ赤な目で私を見てから、私の傷跡にそっと触れる。
「素敵ね、この傷」
ぞくぞくっとした。彼女の言葉の意味がわからない。リストカットの傷跡をそんなふうに言われるとは思わなかった。批判されるか、引かれるか、だからそんなふうに言われるとは思わなくてびっくりした。
「素敵、ですか?」
「えぇ、素敵よ、とっても」
彼女は顔を綻ばせると、ふふと笑った。
「私もリスカ常習者なの」
そう言って、カーディガンの袖を捲った。
これが、みっつ年上の村上麻衣との出会いだった。
麻衣は少し変わった人間だった。
大学三年。私立の大学に通っているらしい。
そうして自己申告だが、同性愛者らしい。この前死ねと言われたのも付き合っていた女性に別れを切り出したら、あんな事件になってしまったらしい。麻衣は、「私のこと気持ち悪い?」と言っていたが、私は、そういうのもありなのじゃない? と答えた。そしたら麻衣はありがとうと微笑んだ。あなたならわかってくれると直感的に思ったの。裕子ちゃんならわかってくれる。
私達は閉店時間になるまで屋上でお話をした。久々に人と会話をしたような気がする。私の両親は共働きで、兄弟はいなく、私は一人っ子。それなりに育てられてきたが、最近は両親とも話をしない。
私にも会話って出来るんだ、ってちょっと嬉しくなった。
麻衣とは携帯の番号を交換した。高校入って最初の友達だ。世の中も捨てたモンじゃない。
「また会ってくれる?」
麻衣は不安そうにそう私に聞いてきた。
「もちろん会えます、リスカを認めてくれる人はいないから、とても嬉しい」
麻衣と私は屋上で他愛もない話を2時間くらいした。
私がまた会えるというと、麻衣は嬉しそうに微笑み、じゃぁメールするね、と言って屋上を後にした。
[次へ#]
[小説ナビ|小説大賞]
無料HPエムペ!
 携帯モード]
[
携帯モード]
[ URL送信]
URL送信]