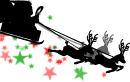多分全国中3のクリスマスといえば、受験受験でこのみじかい15年の人生の中で最も潰れる年なんじゃないだろうか、と、冬季講習2日目の自分は冷静にそんなことを考える。
大阪といえど12月下旬の外なんて凍えるほど冷たくて、室内は室内で地球温暖化対策総無視の暖房器具フル稼動で、ついシャーペンを握る手が汗ばむ。私と同じで教室の他校の受験生も頬を真っ赤にして近頃は大分解けるようになってきた入試予想問題を解いている。
悲しいかな、今年は受験生なのだ。
「よし、今日は終わり!」
塾の先生がパンと両手を叩いてそれが解散の合図。私は一目散に荷物をまとめて教室を出る。と、ザワザワと騒がしい廊下のすぐそこに愛しい彼の姿。
「蔵ー!おまたせ!」
手を振って駆け寄ると「おお、終わったん?お疲れ」と下に降ろしていた荷物を肩にかけ直して微笑む白石蔵ノ介。数々の視線を感じるのは気のせいじゃない、だって蔵ノ介はかっこいいんだから仕方ない。
「お前ほっぺ真っ赤やで、そないに頑張ったんや?」
「あ、う、教室があったか過ぎるんだもん…」
蔵ノ介にケラケラ笑われながら2人で歩く。なるほど頬を押さえれば予想以上にかなりホットだ。
エレベーターは混むから階段で降りることにする、ここ5階だけど。下りだからそこまで辛くもない。私の授業よりひとつ前の授業を取っていた蔵ノ介は、一緒に帰るためにわざわざ自習室で自習して待っていてくれたのだ。
「ていうか今日クリスマスだって知ってた?外のイルミネーションヤバいんだけど。MAXなんだけど」
「あー、窓の外から見えるよな。授業中チカチカ気ィ散ってあかんかったわ」
さすがに真面目な彼にはイルミネーションの光も受験の前では眉をひそめる条件となるらしい。
ちぇ、ステキーとか思わないのか。ちぇ。
そんなことをぶつぶつ思っていると、3階についたところで何やら女子の喋り声が聞こえてきた。
「なぁ〜アタシにもそれ送って!赤外線して!」
「え、こっちが忍足くんでこっちが白石くんやんな?ちょ、白石くん笑とるやん!あかんこれ待ち受けにする!」
「だーめー!蔵様はうちのやもん!」
会話の内容に思わず口元が引き攣ってしまう。声デカい、声デカいよお嬢さん方。半笑いで当の本人を見上げると、「絶頂〜…」と悩ましげな顔をされた。ああそうですね、エクスタシ〜ですね。
「忍足くんもええけど、うちはやっぱ白石くんがええな…白石くんやったら処女あげるわ」
「そんなのアタシもやし!抱いてー蔵様ー!!」
キャー!ととんでもない話題で盛り上がる女子たちの声に、鳥肌が立った。
さっさとその場を離れたくて、いつの間にか脚を止めていた蔵ノ介の腕を引こうとすると、「ちょお待ち」と逆にその手をとられた。「え?」一瞬意味がわからなくて素っ頓狂な声を上げてしまったが、あ、もしかして声デカいで自分らとか注意しに行くんだろうか。女の子たちを。
「蔵ノ介?え、え?あの、」
と、思ったのに全然違って、彼は私の手を引いたまま、大騒ぎする女子のいる隣の空き教室のドアをガララと開けて入った。真っ暗で外のイルミネーションと廊下の電気だけが、差し込む唯一の明かり。
「な、なに?」
「んー?や、あの子らに白石蔵ノ介が誰のモンなのかわかってもらお思て」
「え!?」
暗がりでも判る、彼は今多分満面の笑みだ。私を壁に追い詰めて、着てきた私服のムートンのコートを脱がそうとする蔵ノ介。
「そそそんなことしなくても!ていうかもう9時半だし帰らないと!」
私は焦って蔵ノ介の手を掴み必死に抗議するのに、「なぁ知ってる?」と切り返され軽くスルーされてしまう。
「なにが、」
「クリスマスの夜12時がな、1年で1番セックスする人が多いんやて」
「、、…だ、だから、」
「せやけど俺ら中3やん、15歳やん、12時まで一緒になんて居れへんやん?」
なんとなく話の主旨が読めてしまって、だんだん頬が赤くなっていく私は腐ってもやはり変態絶頂男の彼女なんだなぁと実感してしまう。
「受験生やねんから、これで我慢しいや?」
「…や、」
「今年のクリスマスプレゼントは、女の子のアイドル白石蔵ノ介です」
「ま、待って、ひゃっ!」
蔵ノ介の冷たい指先がブラウスとキャミソールの下を這う。全身が粟立つ。私ははっとして口を手で覆った。
「待たへんよ?」
「〜〜〜っ、冗談でしょ?隣に人いるのに、っ」
「そないなこと言うても…結構満更でもなさそうやで?」
「や、やだっ、やだ!」
蔵ノ介の進む手を拒む。私にはまだ理性が生きているから。
小声で必死に抵抗していると、彼の眉が段々ひそまる。
「…そんなに嫌?」
そして急に耳元でそう呟いたかと思うと、
「!?、…っ、きゃ!」
ぐわっと身体を抱き上げられて、机の上に座らされた。ガタン!と机が音を立てる。一瞬隣の教室の女子たちの笑い声が止む。
ヤバイ、そう思う前に。
蔵ノ介は私の脚の間に入り込み、腰を当てつけた。
「―――!?」
運悪くその日はスカートで。ストッキングも履かず寒々しいことこの上ない格好で。これは私が悪い。蔵ノ介はまるで行為中であるかのように、
「…っや、あっ…!」
布越しに、下着越しに私を揺さ振った。
「…な、にして、んの、バカッ!」
「うっさいわ、自分がやりたくない言うからやろ」
「ッ…」
「せやったらその気にさせるまでや」
ガタガタと机が鳴く、その振動に自分が疼き出すのを認めたくない。なのに、必然的に思い出さざるを得ないあの熱が、だんだんと、中枢を支配しようとする。じわりと滲んできた瞳。私はぎゅっと目を瞑った。
「ダメだよ蔵ノ介…」
「何で、」
「無理、絶対、…絶対声抑えらんないっ」
そう言って、暗いからきっと見えやしないのに、顔を見られたくない一心で蔵ノ介の首に抱きついた。
すると彼はふっと鼻で笑った。ああ、今きっとすごく人を見下すような、勝ち誇った笑顔でいる。もうわかる。彼のそんな一面が見れるのは、テニスの試合中と今みたいなときだけだ。
そして蔵ノ介は私の頭に手を置くと、
「聞かしたらええよ―――思い知らせたろ」
そう耳打ちした。心底愉しそうに。
隣の教室から響く、女の子たちの喧騒が全く耳に届かなくなるまで、きっとあと少し。
「あーあ、10時半過ぎてるよ絶対怒られるよ」
「着いてったろか?ほんでオカンにクリスマスやから甘い夜を過ごしてましたーって」
「絶っっ対来ないで!断固拒否!」
「なんやノリ悪いなぁ…あ、せや、そういえばやってる時な、あの女の子たちしっかり覗いとったで」
「え!?」
「俺目ぇ合ったもん。めっちゃ笑顔向けたったー」
「な、ば、ばばばかっ!何考えてんのこの変態絶頂男!」
「そしたら顔真っ赤にしてパシャパシャ写メってんねん、うけるやろ!んんーっ、絶頂!」
「絶頂じゃないわよこの変態ー!!」
「ま、エクスタクリスマスってことやな☆」
「何っにもかかってないし!」
 そこに愛があるなら
そこに愛があるなら