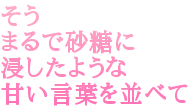うまく言葉に乗せて伝えられない想いを詰めた手紙に返事はいらないとライル・ディランディは思う。
もしも愛の告白を文字に表したとして、目に見えない部分でけれど確実にその手紙は本人が自覚してもいない気持ちを露にする。例えて苺ジャムの瓶詰。甘くてとろけそうな糖度を有するそれは、あまりにも自分らしくないとライルは考えるのだ。
だから返事はいらない。
相手からの手紙を読んで、どう伝わってしまったのかを自覚してしまうから。らしくない自分をどう捉えられたかを感じて、ほんの少しの恥とほんの少しの後悔を残すのが嫌いだから。
「…でも、なぁ…」
ライルは自室のベッドに仰向けに寝転がった状態で、心底溜め息をついた。
手には同じソレスタル・ビーイングに所属しているミレイナ・ヴァスティから恥を忍んで頂戴したかわいらしい猫の柄の便箋。紙面に踊る黒猫は今からいよいよ書き始めようとする手紙の宛て先である刹那・F・セイエイ、その人をどことなく彷彿とさせるような雰囲気を醸しだしていた。
(そもそも手紙を書いたところで、俺はどうしたいってんだよ)(愛なんて語るに甘い関係じゃないのに)
ふと虚ろいだ瞳で天井を見上げればそれこそ答えという存在など見付かりはしないのに、その奥に蠢く宇宙(そら)を見透かした気分になれば曖昧に何かを掴んだ気にさせられる。(刹那との始まりであった兄さんが沈んだ大海なのだからそれも当然かもしれない)そしてライルもその海に捕まった。
ああ、なんて滑稽な。
「ロックオン、ちょっといいか」
不意に何重もの静寂に包まれた声がして、ライルは素早く便箋をシーツの下に隠して身を起こした。けれどそれよりも速く部屋の扉が開くと、件の刹那がその姿をライルの前に晒す。
「ああ…、すまない、仮眠の邪魔をした」
「いや、どうせ起きてたから構わないさ。それより用件は?」
すると刹那は視線をさ迷わせると、
「ミレイナから、ラブレターなら封筒もあった方がいいから選びに来て欲しい、と伝言を頼まれた」
「ラ…っ」
それは違う!とライルは頭を押さえながら心中叫ぶ。だがそういえば便箋を貰う時に「ラブレターですかぁ?」と聞かれた気がする。誰かに便箋のやり取りを見られていないかと気が散漫し過ぎて鮮明にではないけれど。
「ラブレター…、書くのか…?」
ふっと刹那が言葉を零す。
それに今度こそは「書くわけないだろ!」と声高に言い放ち、しかしそれは逆効果だと気付いたのは刹那の苦い表情を目にしてからだった。
「書くんだな」
「あ、いや、…違う。それは違う。ミレイナの…ただの勘違いであって、俺は書くつもりはない」
「…そう、か」
途端に二人を包む空気が重く垂れ込んだ。
ラブレターは書かないと自分は言った。けれどミレイナはとても勘の良い少女だから手紙の行く末はあながちそれだけではないように思う。そしてラブレターは嫌いだという考えにも変わりはないが、しかしてペン先が誘うところとはライルにも理解し難かった。
(どうしたもんかな)ふと困り果てた瞳で刹那を見上げれば彼の名のようにほんの一瞬だけ視線が交わり、その色は自分には似つかわしくないあの苺ジャムに存外通じるものがあった。けれど彼にはそれがとてもよく似合う。
どうしてかおかしくてライルは笑い出すと、向かい合う刹那は理解し兼ねるように小首を傾げた。
「お前の行動はいつも唐突だな」
「褒めてんのか?」
「いや、呆れてる」
そう言うけれど刹那もまたライルに釣られたようにふっと微笑んだ。同時にライルは(そうか、こいつがこの笑顔を向けてくれるのは俺だけなのだから)幸せの見返りを彼にも与える為に自分は便箋を手に取ったのかもしれない、と考えた。口に乗せて言うにはほんの一言で終わってしまうから、伝えたい丈を全て詰め込むように文字に化けさせる。
脳髄から心臓へ、手の平から爪先へ。
「だがそんなお前を、俺は――…」
刹那が口から放つ。その言葉はライルが手紙に添えるしかない気持ちを真っ直ぐにライルへと届けた。気高く美しく、尚且つ甘くて何もかも包み込むような。
ライルは歪む世界を感じながら、
「やっぱりラブレターは書くよ」
漫然と微笑んだ。
今この気持ちすらも彼へと届くようにと願いながら。
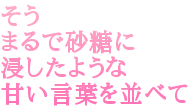
(だけれど返事もやっぱりいらない)
(1222)
thanks.僕の世界は君のもの!