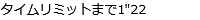
「転校?」
「ああ、親父の都合でな」
何事もない日常が始まって、終わる、はずだった。
彼の言葉は部室をどよめかせ、驚かせた。
「そんな・・・いきなり・・・です・・・」
「すいません、朝比奈さん。急に決まったもんでして・・・」
えぐえぐ、と涙を零す朝比奈さんを優しく諭す彼の表情はどこかすっきりしているように見えた。
いつも本から目を外そうとはしない長門さんでさえ、今は彼の方を凝視している。
「寂しく、なりますね」
と、僕も言った。
寂しくなる。とても。嘘、じゃない。
彼は部室を見渡して、"随分あの時とも変わったもんだ"とため息交じりに笑った。
そして、パソコンの前まで歩いていく。そこには、一人の少女が伏せた状態で座っていた。
「おい、ハルヒ」
「・・・」
「・・・楽しかったよ」
何も言わない彼女に対して、彼は深いため息をついて
「最後まで、お前はそうなんだな」
と、困ったように笑って言った。
最後に、彼は彼女の頭を2、3度軽く叩いて"じゃあな"と言った。彼女は、何も言わなかった。
「後のことはよろしく頼む」
「うっ・・えぐ・・げ・・元気でいてください・・・ね」
「・・・さよなら」
「今まで、ありがとうございました」
彼は"おう"と一言言うと、いつもより2倍ぐらい大きくなった鞄を抱えて部室を出て行った。
扉が閉まった後に残ったのは、朝比奈さんのすすり泣く声と、パソコンのモーター音だけで、僕は一瞬ここは閉鎖空間なんじゃないかと疑った。
閉鎖空間ができてもおかしくない、状況下なのだから。
僕は未だに伏せた状態でいる彼女に目をやる。
これは防がなければならない事態、ではあった。
"凉宮ハルヒ"という"神様"の存在から、それを支えていた"凡人の男子学生"を失くした今、僕たちに待っているこれからのことは予想ができない。
では、なぜ、僕たちはそれを止めることができなかったのか。否、しなかったのか。
それは、これが決まっていたこと―既定事項―だったから。正確に言うならば、決めてしまったこと。だったから。
決めてしまったのは、涼宮ハルヒでもなく、朝比奈みくるでもなく、長門有希でもなく、そのバックについている様々な監視役でもなく、たった一つの恋心を叶えたいがために役目を捨ててしまった古泉一樹。そう、僕。
「涼宮・・・さん」
僕は、彼女の元に歩み寄り、彼女の名前を呼んだ。
「キョン君がいない寂しい気持ち・・・お察しします」
彼女は声を押し殺してはいるが、泣いているようだった。朝比奈さんの泣き声で聞こえなかったのだろう。
彼女は掠れた声で"キョン"と彼の名前を呼んだ。
彼を失くした所で、僕の位置は何も変わらないということは気づいていた。
ただ、この世界がキョン君に出会うまでの世界に戻る、またはそれ以上に悪い世界になる、そんなデメリットだらけの選択だとは分かっていた。
「・・・僕では、駄目、ですか?」
そう言って、そっと抱きしめた彼女の体は予想以上に小さかった。
耳元で途切れ途切れに聞こえる彼の名前に、僕は目を瞑って、心の中で"こんな世界を願ってしまって、申し訳ありません"と呟いた。
しかし、いくら僕がそれを望み、何らかの能力―あまり公には出せないことだ―を使って、彼を転校させたとしても、SOS団という関係を、涼宮ハルヒという人間の重要さを一番よく知っている朝比奈さんや、長門さんが黙っているわけはない。
ただ、関係を分かっていたからこそ、この世界が実現してしまったのかもしれない。
これは僕の憶測に過ぎないことではあるが、そう、きっと彼女たち自身も彼のことが好きだった。
だから見て見ぬフリ、なんて洒落たマネをしてくれたのかもしれない。(現に今も僕が彼女を抱きしめていることに関して反応を示さないようにしているようだ)
こんな世界にしてしまった僕を機関は黙っていないだろう。きっと。
それでも良かった。ただ、最後に彼女を抱きしめたかった。欲を言えるとしたら、彼の名前ではなく僕の名前を呼んでほしかった、けれど。
機関にこのことが気づかれる、その瞬間までは彼女をこの腕の中に。どうか。
古泉一樹の消失まで、残り1秒22。
