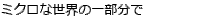
今彼女の見える世界には何憶という情報が見えているのだろう。
強奪してきたパソコンの前で、不満そうな顔をしている女子生徒を僕は見つめた。
「なんで古泉くんしか来ないのよ!」
僕は、そのまま彼女を見つめて笑った。
「僕だけでは不服でしょうか?」
そんな自虐的な冗談を飛ばしてみたりして、彼女の反応を覗おうとしている僕はもしかしたら腹黒いのかもしれない。
彼女はそのまま不満そうな顔で、僕の方を見て"別にそういうわけじゃないけどね"と言った。十分不服そう、に見えた。
僕はオセロの白を黒にかえて―もちろん、一人オセロである―、休み時間に聞いた記憶を頼りに彼女にその情報を伝える。
「朝比奈さんは鶴屋さんに頼まれた用事があるようです」
彼女は僕の言葉を聞いてか聞かずか立ち上がり窓を開けて外を見ていた。
「長門さんはお隣に行かれていると思います」
彼女は微動だにしない。強いて言うなら風によって柔らかそうな髪の毛が揺れたぐらいだ。
「キョン君は妹さんが熱を出したようで看病の為に帰りました」
「それは知ってるわ」
「これは失礼」
相変わらずキョン君のことになると、神様の中の何らかのセンサーが反応するのだなあ、と実感した。
彼女のフォーカスはやっぱりキョン君にあっているようだ。僕のフォーカスが彼女にあっているように。
それを実感するのと同時に、やはりいつもの何とも言われないもどかしい感情が生まれ始めて、いつもの笑みを崩しそうでオセロ盤を見た。
すると、彼女は僕の向かいの席―いつもはキョン君が座っている席―に座って、僕の一人オセロを、じ、と見つめた。
「・・・古泉くんって頭が良いのに何でいつもキョンに負けるのか不思議だったの」
パタ、とオセロを返しながら、彼女の顔を見る。
相変わらず、彼女の瞳はきれいだった。
「・・・そこよ!」
「はい?」
「そこを取ったら、相手にここを取られて負けちゃうのよ」
彼女は僕の手をオセロ盤から退かせ、彼女自身の手でオセロを返していく。
あっという間に盤上は一色で染まった。
「涼宮さんは、分かるのですか?」
「分かるっていうか・・・古泉くんはスキが多いのよね」
僕は苦笑する。彼女は頬杖をついて、オセロ盤からまた外へと目線を移す。
その儚くて力強くて輝いた目はやっぱりきれいだった。もちろん世辞なんて抜きで。
「・・・散歩、行きますか?」
冗談のつもり、ではあった。
彼女が僕と、並んで歩くわけがないだろう。腹黒なだけではなく意外とマイナス思考なのかもしれない。
「たまにはいいかもね」
彼女は僕の目を見て、少し卑しい笑みを浮かべた。予想外だった僕はどう反応していいのかも分からずに、暫し硬直する。
「何か面白いものが見つかるかもしれないし」
「あ・・・そうですね」
「そうと決まれば早く行きましょう!」
彼女は勢いよくイスから立ち上がる。その勢いに耐えられなかったパイプイスは後ろに倒れた。
まるでどこかの苦労人を見ているようで僕は笑みを零した。部室から出るときに見たパイプイスは襟首を掴まれて引っ張られている苦労人によく似ていた。
もう季節は冬だが比較的外は温暖な気候だった。
今思えば、こうやって彼女と並んで歩くのは初めてかもしれない。夢に見ていたことでもある。
「涼宮さんは普段何を見ているんですか?」
「何でも見てるわ。風景も人も。面白そうなものを探さなきゃいけないもの」
僕は"そうですか"と笑いながら言った。
彼女は"ええ!"と至極楽しそうな表情を浮かべた。僕が一番好きな表情である。
しばらく歩くと、彼女の喜びそうなモノが目に留まった。
「・・・あ!屋台が出てる!行きましょ!!」
こんな季節、こんな場所に屋台が出ているなんて。と、僕は思った。
しかもそこに書いてあった文字が"氷"だ。あまりにも滑稽な光景だった。
「何でこの季節にかき氷なんて売ってるのかしら!!」
そう言うと彼女は駆け出した。スカートが翻る。
これは矢張り彼女が望んで創り出したモノなのだろうか。
それとも退屈がっているだろうと思った誰かの策略だろうか。(例えば、今は恐らく部室の隣で物凄い力を発揮してるであろう寡黙な少女、とか。)
僕は屋台の主人と話している涼宮さんを見て思った。
涼宮さん、あなたの目には一体何憶の情報が映っているのですか?・・・その中で僕は何番目に大きな情報なのでしょうか?
僕の中の世界はあなたです。
でも、あなたの中ではきっと、世界のミクロ単位の一部分に過ぎないのでしょうね。
